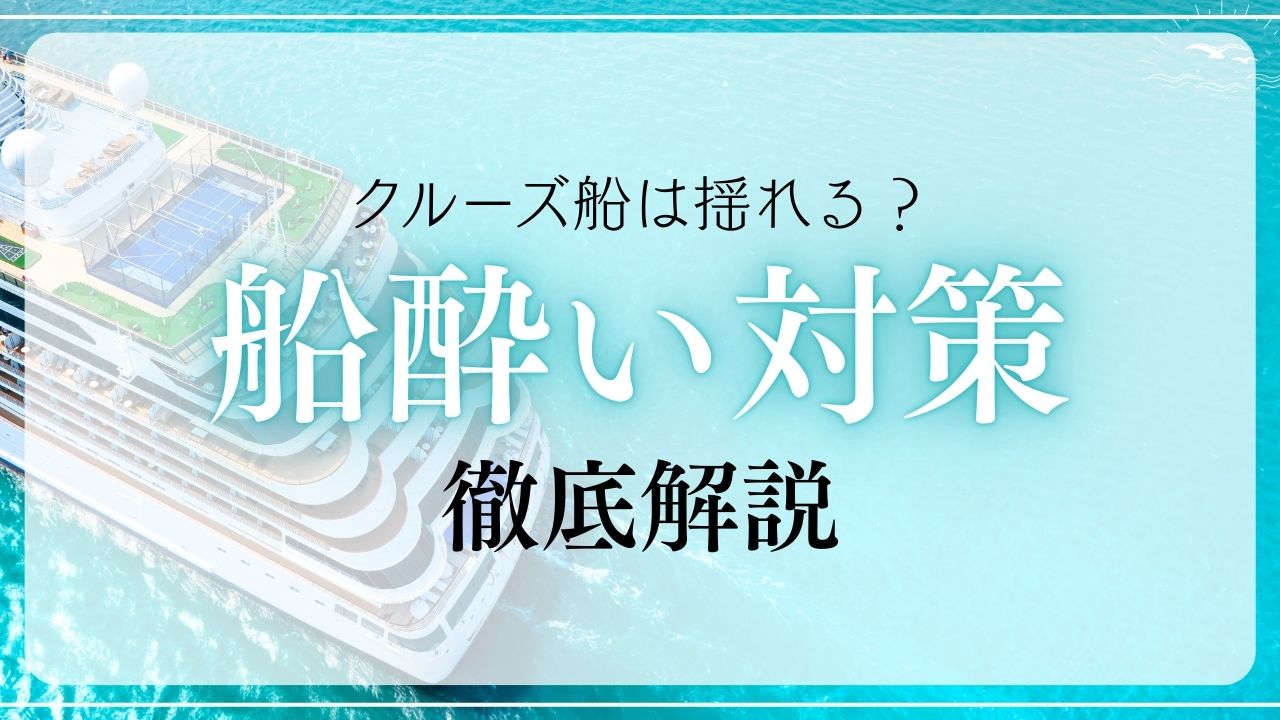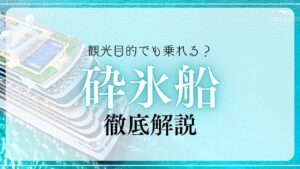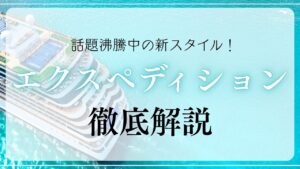クルーズ旅行を計画する際、多くの人が抱える不安の1つが「船酔い」ではないでしょうか。
実際にクルーズ船はどれくらい揺れるのか。そして、もし船酔いしてしまったらどう対処すればいいのか。
……そんな心配から、クルーズ旅行に踏み出せない方もいるかもしれません。
しかし、ご安心を。
現代のクルーズ船には揺れを最小限に抑えるための最新技術が搭載されており、適切な対策を講じれることで、船酔いの心配なく旅を楽しむことができるんです。
この記事では、クルーズ船の揺れのメカニズムから、乗船前・乗船中の具体的な船酔い対策まで徹底的に解説します。
船はなぜ揺れる?|揺れの種類とメカニズム

Photo by iStock
前提として、クルーズ船が揺れるのは、波や風、潮流といった自然の力が原因です。
ここでは、揺れの種類と名称についてご紹介します。
ローリング(横揺れ)
「ローリング」は、波を船の側面から受けた時に起こる、左右への揺れです。
船酔いの原因として最も一般的で、特に波が高い時や、時化(しけ)などで風が強い時に感じやすい傾向にあります。
ピッチング(縦揺れ)
「ピッチング」は、船が波を真正面から受けた時に起こる、前後への揺れです。
ジェットコースターのように上下する感覚が近く、船首から船尾にかけて大きく揺れを感じます。
なお、上下方向への往復運動は、ピッチングとは別に「ヒービング」と呼びます。
クルーズ船の揺れ対策
本記事冒頭でもご紹介した通り、クルーズ船には様々な”揺れ対策”が施されています。
ここでは、そんな対策の一例をご紹介。不安払拭の一助となれば幸いです。
航路の検討
第一に、クルーズ船では、できるだけ揺れが少ない海域に配船されるようスケジュールが組まれています。
定時運行を重視する輸送専門のフェリー等とは異なり、クルーズ船はあくまで乗船客の”体験”を重要視する客船です。
レストランで食事中に皿やグラスが床に落ちるような事態を避けるため、綿密な航海計画が事前に立てられています。
巡航速度
クルーズ船は、事前の航海計画のみならず、その時の状況に応じた対策も講じています。
波が立っている際は、航海速力を落として運行するなど、揺れが最小限に抑えられるよう臨機応変に対応されているのです。
フィンスタビライザー
「フィンスタビライザー」は、多くの大型クルーズ船に搭載されている、魚のヒレ(=フィン)のような装置です。
日本人によって発明されたこの装置により、昨今のクルーズ船は横揺れが大幅に低減されています。
船酔い対策|事前準備
「船酔い」は、三半規管が感じる揺れと、視覚情報とのズレによって引き起こされます。
ここでは、そんな「船酔い」を防ぐための事前準備についてご紹介。
クルーズ船や、キャビンの選び方についても解説しています。
クルーズ船の選び方
大型船は波動を吸収し、船体の揺れを低減させます。
乗り物酔いが不安な場合は、単純に「大きな船を選ぶ」という対策もおすすめです。
キャビンの選び方|揺れない場所はどこ?
揺れを最も感じにくいのは、船体の重心に近い中央のデッキや、海面に近い下層のデッキです。
一方で、船首や船尾は揺れやすいスポットのため、可能な限り避ける方が無難でしょう。
酔い止めの活用
シンプルかつ強力な対策として、乗り物酔いをしやすい体質の方は特に、事前に酔い止め薬を用意しておく方が良いでしょう。
また、船によっては無料で酔い止めの薬、パッチ、注射などが用意されている場合もありますが、外国船の場合は当該国用の容量で処方されることが多く、日本人には効き過ぎてしまう可能性も。
したがって、仮に「無料で酔い止め薬を用意」との文言が記載されていても、過信せず自前で用意する方が無難です。
食事の調整
乗船前は、消化に良い軽めの食事を心がけましょう。
脂っこいものやアルコール類の摂取は船酔いを助長する可能性があるため、控えるのが賢明です。
船酔い対策|乗船中
-1024x683.jpg)
Photo by iStock
窓の外を見る
乗船中に船酔いを感じ始めたら、すぐに遠くの水平線を見つめましょう。
視覚情報と揺れのズレを修正する効果が期待できます。
新鮮な空気を吸う
気分がすぐれない時は、無理をせずデッキやバルコニーに出て風に当たりましょう。
新鮮な空気を吸うことで気分がリフレッシュされ、船酔いの症状が和らぐことがあります。
無理せず横になる
船酔いの症状がひどい場合は、無理をせずキャビンに戻り、静かに横になって休みましょう。
横になることで平衡感覚が安定し、症状が落ち着くことが多いです。
お酒の力を借りる
上記方法で解決しなければ、お酒の力を借りて寝てしまうという選択肢もあります。
ただし、アルコールは脱水症状を招き、船酔いを悪化させる可能性もあるため、体調を考慮して無理のない範囲で試すようにしましょう。
本記事のまとめ
最新のクルーズ船には揺れを抑える技術が備わっており、”ほとんど揺れを感じない船旅”が実現しています。
それでも、その日の波の状態や天候によっては、どうしても可能性も0にできないのが自然の難しいところ。
”揺れ”が心配な方は、本記事でご紹介したような事前準備を試してみてはいかがでしょうか。
「よいたび。」クルーズ特集
「よいたび。」では、新しい旅のスタイルである「クルーズ旅行」の魅力を広めるため、様々な記事を作成・公開しています。
クルーズ|関連記事
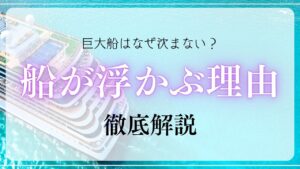
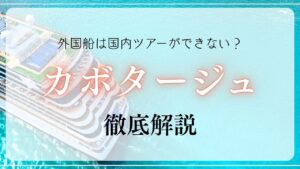
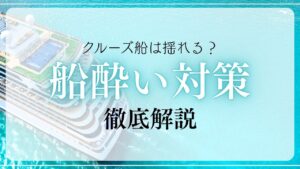
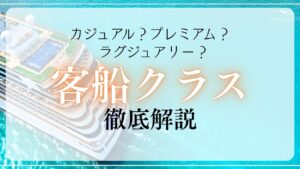
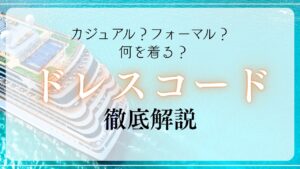


クルーズ|おすすめブック
話題のクルーズ船を一括でチェックするなら、るるぶの『クルーズのすべて』がおすすめです。
るるぶクルーズのすべて2025~2026 (JTBのムック)